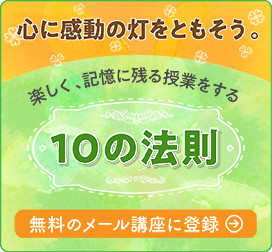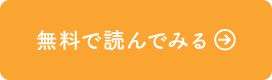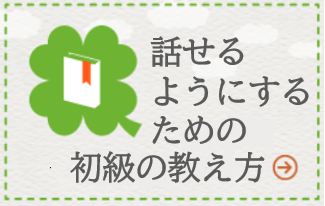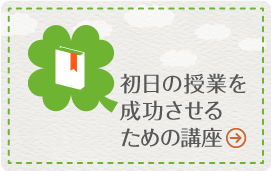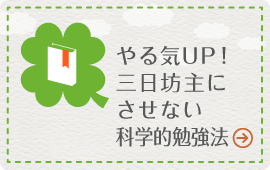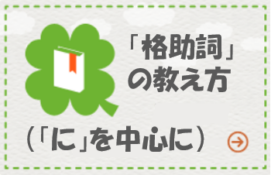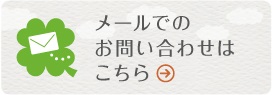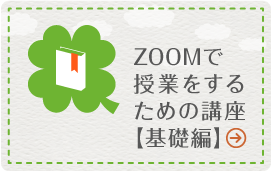「て形」の意味・用法(その1)
「て形」の本質とは?
(1)浅草に新しい駅ビルができた。
(2)そのビルの一階は
・・・・・・いつも観光客でにぎわっている。
ーーー(1)と(2)の文をつなげますーーー
(1)+(2)⇒
・・・浅草には新しいビルができて、
・・・・そのビルの一階は
・・・・いつも観光客でにぎわっている。
上記のように
●「て形」は二つの文をつなげ、
・・一つの文にまとめるときに使います。
●「て形」は文と文をつなげる、
・・一番やさしい形と言えます。
以下の例文のように、
動詞、イ形容詞、ナ形容詞、名詞は
「て形」を使って、前文と後文をつなげることができます。
動詞 → 傘を持って、出かけます。
イ形 → この子犬は小さくて、かわいらしい。
ナ形 → iPhone は お年寄りには機能が複雑で、使いにくい。
名詞 → トムさんは今、子供が病気で、とても忙しい。
「て形」の基本的な働きとその意味解釈
「て形」の基本的な働き
「て形」の基本的な働きは
「単文と単文をつなぎ、複分を作る」ことです。
前の文を従属節、後の文を主節と言います。
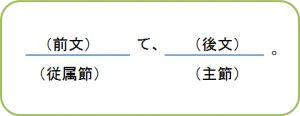
日本語は 文、最後の述語が一番大切です。
そこで、後件の文を主節と言います。
では、前件の文をどうして従属節と言うのでしょうか。
次の例文を見てください。
(例1)浅草へ行って、友達に会います。
(例2)浅草へ行って、友達に会いました。
(例1)はこれからのこと。(⇒会います)
(例2)は過去のことです。(⇒会いました)
しかし、
前件の「行って」は(例1)でも、(例2)でも同形です。
前件の「行って」には、現在、過去の意味はないのです。
前件の「行って」には、現在も過去もないのですが、
(例1)では、主節の述語が現在形(会います)なので、
「行って」が現在形の意味になります。
(例2)では、主節の述語が過去形(会いました)なので、
「行って」が過去の意味となります。
つまり、
前件の「行って」は、主節の述語に支配されているのです。
前件の「行って」は、主節の述語に従属していると言えます。
そこで、
「行って」のある前件を、従属節と言います。
「て形」の意味解釈
(例1)これは高くて買えません。
(例2)これは高いので、私には買えません。
(例1)を見てください。
「高い」のて形「高くて」までを考えます。
ここまでだけでは、
その文がどんな意味をもつのかは、わかりません。
しかし、
(例2)の「高いので」はどうでしょうか。
「高いので」の一語だけで、
「~ので」がありますから、前の文と後ろの文の関係は、
すぐに「理由」だとわかります。
つまり、
「て形」は、それだけでは、
前の文と後ろの文の意味関係を表せません。
「て形」それ自体には、意味がないのです。
しかしながら、
「て形」には実に多くの用法があります。
「て形」自体に意味がないので、多くの用法があるともいえます。
なぜなら、
「て形」でつないだ前文と後文を見て、
初めてその文全体が、どんな意味なのかを解釈するからです。
そのことを具体例をあげて見ていきましょう。
継起 vs 原因・理由
(例1)駅まで歩いて、電車に乗った。
(例2)駅まで歩いて、足が痛くなった。
(例1)と(例2)の前件の文は同じ、
「駅まで歩いて、」です。
しかし、
前件、後件の文を両方とも読むと、
(例1)と(例2)の用法は違うと直感的に判断できます。
(例1)は駅まで「歩く」、それから、電車に乗る。
前件の動作「歩く」の次に、後件の動作「乗る」が起こっています。
そこで、
これは「継起」の「て形」だ、と解釈します。
継起(けいき)とは
「継起(けいき)」とは、聞きなれない言葉だと思いますが、
日本語文法の中では、よく出てきます。
「継起」という漢字を見てください。
これは、
前件の動作に継(つ)いで、後件の動作が起こる、
と言う意味です。
では
(例2)駅まで歩いて、足が痛くなった。
これはどうでしょうか。
「駅まで歩いた」 → 「足が痛くなった」
見れば、すぐに判断できますね。
足が痛くなった原因は、駅まで歩いたからです。
そこで、
(例2)は「原因・理由」の「て形」だ、と解釈します。
継起 vs 付帯状況
(例1)母はゴム手袋をはめて、食器を洗い始めた。
(例2)母はゴム手袋をはめて 食器を洗っている。
(例1)と(例2)の前件の文は同じ、
「ゴム手袋をはめて」です。
しかし、
前件、後件の文を両方とも読むと、
(例1)と(例2)の意味・用法は違う、
と、こちらの文も直感的に判断できます。
(例1)はゴム手袋を「はめる」、それから、食器を洗い始めます。
前件の動作「はめる」の次に、後件の動作「洗い始める」が起こっています。
そこで、
これは「継起」の「て形」だ、と解釈します。
では
(例2)母はゴム手袋をはめて 食器を洗っている。
これはどうでしょうか。
前件「ゴム手袋をはめて」と
後件「食器を洗っている」の動作は
平行して起こっているように感じます。
ゴム手袋をはめた状態で、食器を洗っている、と理解されます。
そこで、
(例2)は「付帯状況」だ、と解釈します。
付帯状況とは

<付帯状況イメージ>
「付帯状況」とは、あまり耳慣れない言葉だと思います。
これも「継起」同様、
日本語文法の中では、よく使われます。
「付帯」の意味は主となる事柄にくっ付いて、
そうした状態を帯(お)びる、ということです。
つまり、
「付帯状況」とは
主となる事柄に、もう一つの事柄がくっ付いている状況(状態)のことです。
(例2)母はゴム手袋をはめて 食器を洗っていた。
(例2)の解説
⇒日本語は文の最後に重要事項が来ます。
つまり、
「食器を洗っていた」という後件の文が「主」となる事柄です。
そこにくっ付いているのが
「ゴム手袋をはめている」という状態です。
(例2)の意味は
母はゴム手袋をはめた状態で、食器を洗っている、
ということです。
これを「付帯状況」の用法と言います。
今までの「て形」の役割と意味・用法のまとめ
●て形の基本的役割は
「単文と単文をつなぎ、複分を作る」ことです。
●て形の意味・用法は
前後の文脈によって決まります。
つまり、
「て形」の意味・用法は前後の文脈で、分類します。
(例1)継起
●駅まで歩いて、電車に乗った。
(例2)原因・理由
●駅まで歩いて、足が痛くなった。
(例1)継起
●母はゴム手袋をはめて、食器を洗い始めた。
(例2)付帯状況
●母はゴム手袋をはめて 食器を洗っていた。
次回は
「て形」の「原因・理由」について、
詳しく見ていきます。
ではではニゴでした。